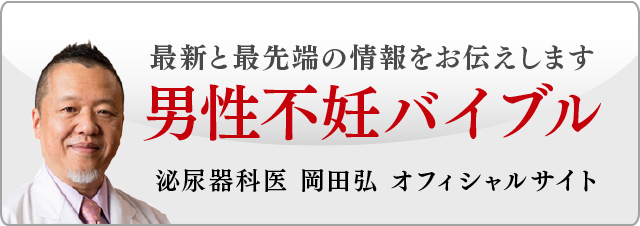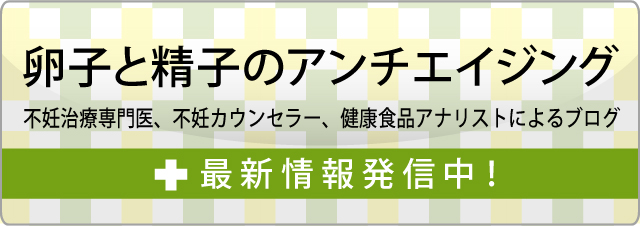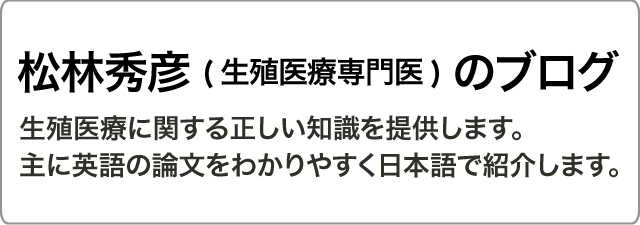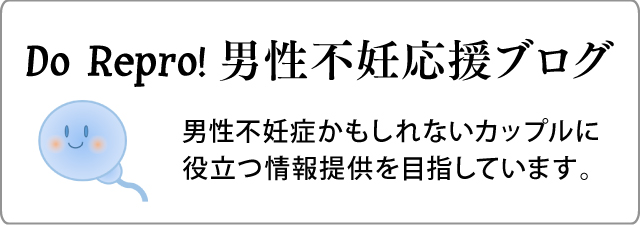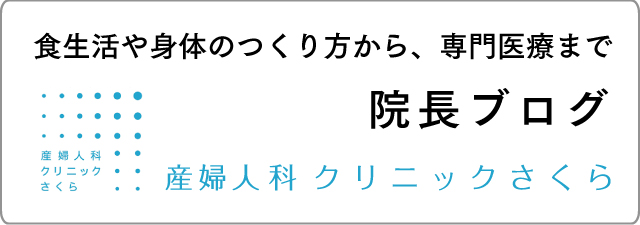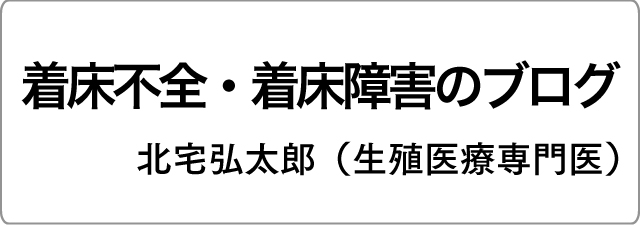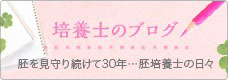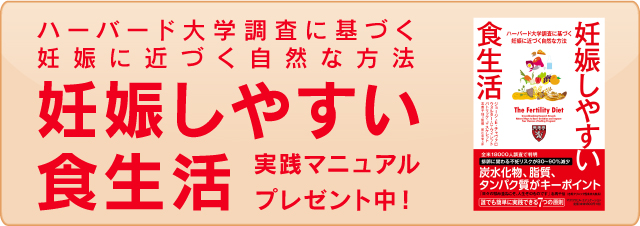妊娠中の母親や、生まれた子供のビタミンD濃度が低いことは、その後の神経発達障害の発症リスクと関連しているとの報告が多くなされています。
今回デンマークで行われた研究では、子供のビタミンD濃度として2つの指標(25(OH)DとビタミンD結合タンパク質(DBP))を使い、6つの精神疾患のリスク、また遺伝的要因との関連を調べました。
1981年から2005年の間にデンマークで生まれた全ての赤ちゃんを対象とした研究「iPSYCH2012サンプル」に含まれる、新生児71,793名の血中ビタミンD濃度のデータが使われました。そして2012年12月31日までにその個人が診断された、大うつ病性障害(抑うつ気分、興味の減退、認知機能の障害、ならびに睡眠障害や食欲障害などの自律神経症状を特徴とする精神疾患)、双極性障害、統合失調症、ADHD、ASD、神経性食欲不振症の6つの疾患との関連が調査されました。
また追加の調査としてビタミンD濃度に関連するとされる遺伝的な要因と6つの精神疾患についても解析が行われました。
2012までの追跡で診断されたのはそれぞれ、大うつ病性障害が24,240人、双極性障害が1,928人、統合失調症が3,540人、ADHDが18,726人、ASDが16,146人、神経性食欲不振症が3,643名でした。
分析の結果、新生児期のビタミンD濃度(25(OH)D)と統合失調症、ASD、ADHDの間には相関があることがわかりました。またDBPが低い赤ちゃんでは統合失調症発症リスクが高いことがわかりました。
またビタミンD濃度に影響するとされる遺伝的要因との関連では、遺伝的要因によってビタミンD濃度が高くなる傾向のある人ほど、ASDと統合失調症のリスクが低いことがわかりました。またビタミンD結合タンパク質が少ない遺伝的特徴を持つ人ほどADHDの発症リスクが高いことがわかりました。
以上のことから、新生児期のビタミンD濃度が精神障害の発症リスクと関連していることが明らかとなり、新生児期にビタミンDを充足させることで長期的な精神発達障害の発症リスクを低減させる可能性が示されました。
コメント
ビタミンDは、脂溶性ビタミンの一種で、長らく骨の健康に関連することが知られていましたが、この20年の研究で、妊娠や出産に極めて重要な役割を担っていることがわかってきました。
ビタミンDが不足すると、不妊治療でも、自然妊娠でも妊娠率が低下したり、妊娠後の母子の健康にマイナスの影響を及ぼしたりするのです。
母親のビタミンD濃度は、胎児のビタミンD濃度に影響します。そして今回の研究でわかったのは、それが生まれた子供の長期的な精神疾患の発症リスクにまで影響するということでした。
一方私たちに必要とされるビタミンDのほとんどは、紫外線にあたることで体内でつくられています。日本人の女性は紫外線を避ける傾向にあるため、生殖年齢にある、ほとんどの女性で不足していることが知られています。
妊娠を希望される女性は、適度に日光にあたり、魚やキノコを積極的に食べることはもちろん、サプリメントの利用も検討してみるとよいかもしれません。