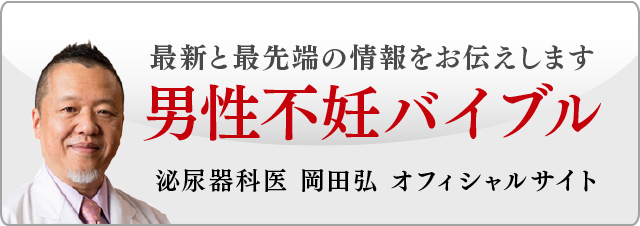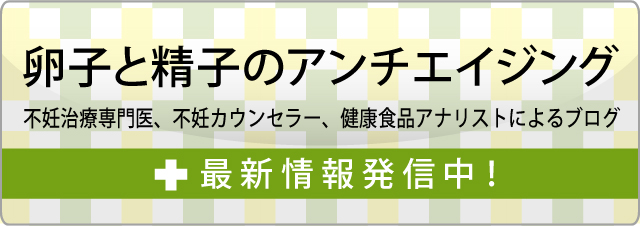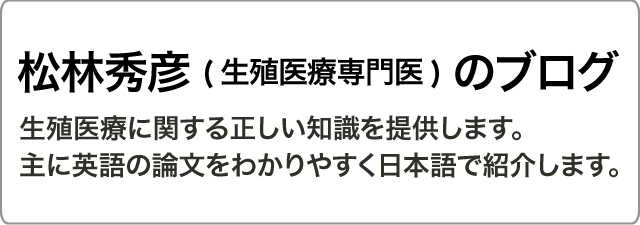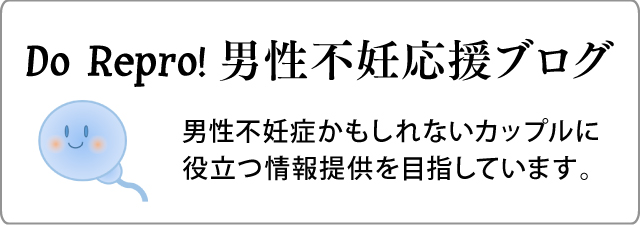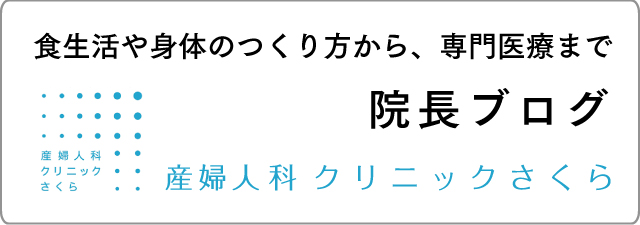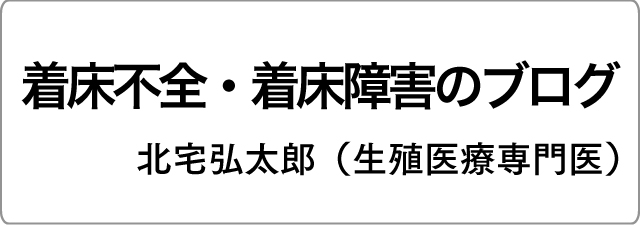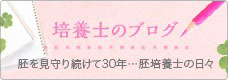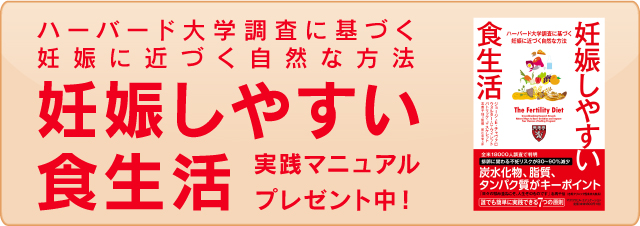妊娠中の母親の食事が胎児の神経発達に影響を及ぼすことは、これまで多くの研究によって示されています。ただし朝食と生まれた子供の神経発達の関係について調べた研究は多くありませんでした。
そこで福島県立医科大学の研究グループは、エコチル調査*のデータから妊婦の朝食を摂る習慣と生まれた子供の3歳時点の神経発達の関連を調べました。
2011年から2014年にかけて単胎出産した72,260人の女性を対象とし、妊娠中期~後期に実施した食事に関するアンケートから朝食の摂取頻度や1日の総エネルギー摂取量を調べました。
一方、出生児の3歳時点の神経発達については、ASQ-3(Ages and Stages Questionnaire・第3版)を用いて調べました。このテストは、コミュニケーション、粗大運動(腕や足などの大きな筋肉を使う動き)、微細運動(手指の細かい動き)、問題解決(手順を考えて行動するなど)、個人と社会(他人とのやり取りに関する行動等)の5つの領域について、両親の回答をもとに子どもの発達をスコア化し、評価するものです。この5つの項目にはそれぞれ基準値が設けられています。
調査の結果、朝食を毎日摂る習慣のある妊婦(53,124名)は、朝食を摂る習慣のない妊婦(19,136名)と比較して、出生児の3歳時の「コミュニケーション」領域で基準値に満たない割合が13%低いことがわかりました。
また一日の総エネルギー摂取量との関連についても調べたところ、一日の総エネルギー摂取量が1,800kcalと最も多いグループでは、母親が妊娠中に朝食を摂る習慣があると「個人と社会」の領域で基準を下回る割合が16%低いことがわかりました。しかし子どもの性別との関連ともあわせて調べると、この傾向は男児で顕著に表れました。その他の領域においても子どもの性別によって、関連の強さに差がみられました。
以上のことから、朝食は 一日の栄養摂取において重要な役割を果たしており、妊婦の食事の質が向上することで、胎児にも神経発達に重要な栄養素の供給が増え、精神神経発達に良い影響を与えたのではないかと考えられます。
ただし、この研究では朝食の内容や朝食のみのエネルギー摂取量、また子供自身の朝食習慣については調べられていないことから、母親の朝食と子供の神経発達の関連についてはさらなる研究が必要です。
*環境省によって実施されている、母親の生活習慣と出生児の健康の関係を調べる研究
コメント
母親が妊娠中に朝食を摂る習慣があるかどうかで、その後生まれた子どものコミュニケーションや社会的な分野での神経発達に差が見られたという研究です。
「朝食」は、単に朝に食べる食事であるということだけでなく、重要な役割を担っています。
まず、朝食は体内時計をリセットします。体内時計は生体リズムの司令塔で、女性の生殖機能はリズムとタイミングが全てと言っても過言ではありませんので、朝食の欠食は生体リズムのずれにつながる可能性があります。
また、朝食を食べることで1日の食後の血糖値が安定します。そのため、朝食を抜くと昼食後と夕食後の血糖値が高くなり、糖尿病の発症率が高くなることが知られているほか、食後高血糖は卵胞発育によくない影響を及ぼすこともわかっています。
さらに、朝食は体温を上げます。体温は朝に最も低くなり、起床後、徐々に上がっていきますが、朝食を食べることで「熱」が産生され、体温が「スムーズに」上昇します。
このように朝食の欠食が、さまざまな面から生殖機能にマイナスの影響を与えることにつながります。
今回の研究では、朝食を摂ることが女性の生殖機能のみならず、生まれた子供にも良い影響を及ぼすかもしれないというものでした。
自分や未来の家族のために、早く寝て、早く起き、朝食を食べることが大切です。