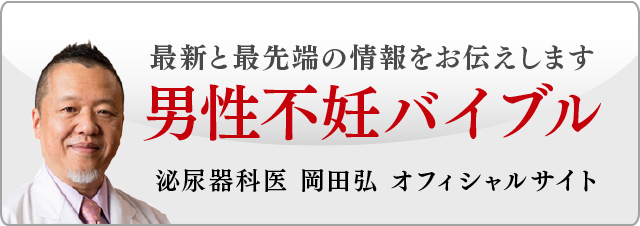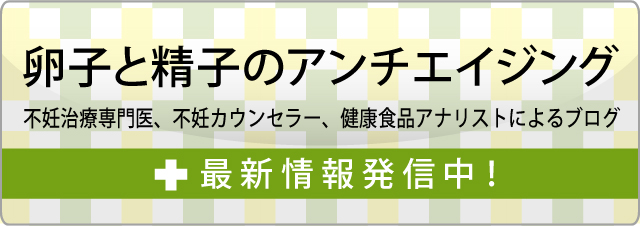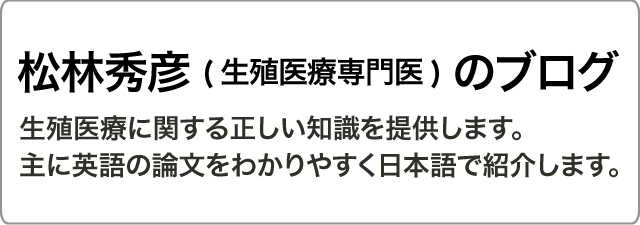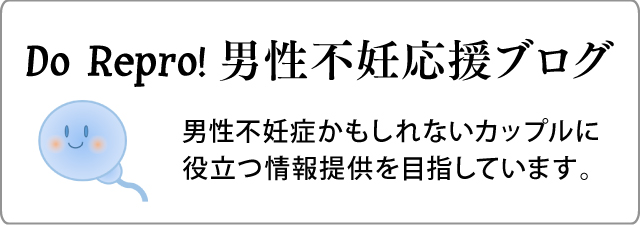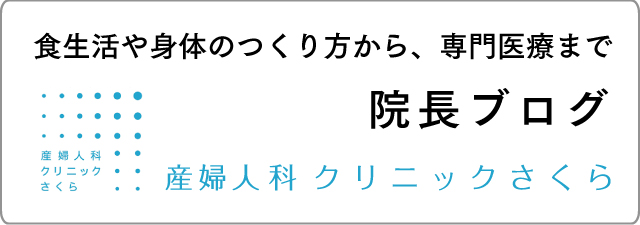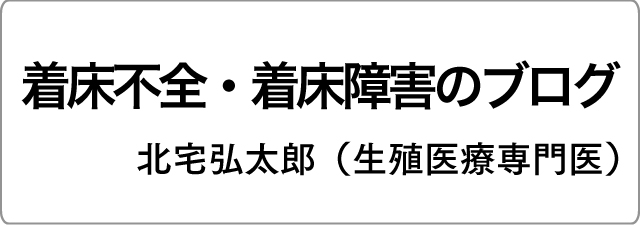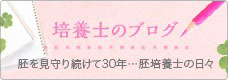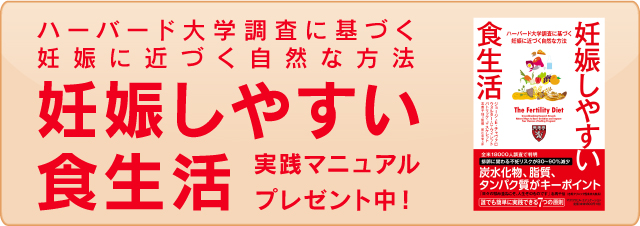生活習慣・食事・サプリメント
18.03.04
妊娠中・授乳中の食と出生児のアレルギーリスク:メタ解析
妊娠後期や授乳中にプロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌など)のサプリメントを摂取することは出生児の湿疹のリスクが、妊娠中や授乳中にオメガ3脂肪酸(DHAやEPAなど)のサプリメントを摂取することは出生児の食物アレルギーのリスクが、それぞれ低下することを示唆する研究報告がなされました。
18.02.25
ART女性患者の運動と妊娠率、出産率:メタ解析
体外受精や顕微授精の女性患者の治療周期前の運動は、高い妊娠率や出産率に関連することが中国で実施されたメタ解析の結果、明らかになりました。
18.02.18
砂糖入り清涼飲料水の摂取量と自然妊娠確率との関係
カップルのいずれかが1日に1本以上の砂糖入り清涼飲料水を飲むことは自然妊娠率の低下に関連することがアメリカで実施された研究で明らかになりました。
18.01.30
地中海食と体外受精の妊娠率、出産率
35歳未満で非肥満の女性では、地中海食に近い食べ方(地中海食スコアによる定義)をすることは体外受精の良好な妊娠率や出産率に関連することがギリシャで実施された研究で明らかになりました。
18.01.23
人工甘味料と体外受精治療成績は関連するか?
1日に3本以上の清涼飲料水、あるいは、1日に1本以上のダイエット清涼飲料水や人工甘味料入りのコーヒーは顕微授精の治療成績の一部にマイナスの影響を及ぼす可能性のあることがブラジルの研究で明らかになりました。
18.01.18
生活習慣・食事・サプリメント男性の妊娠させる力に影響を及ぼすもの
肥満の男性不妊患者における精液所見と微量栄養素の関係
肥満男性ではBMIや微量栄養素濃度が精液所見と関連することがスペインの研究で明らかになりました。
18.01.06
妊娠前後の葉酸やマルチビタミンサプリメントと子の自閉症リスク
妊娠前、妊娠中の母親の葉酸やマルチビタミンサプリメント摂取は子どもの自閉症スペクトラム(ASDs)のリスクの低下に関連することがイスラエルで実施された研究で明らかになりました。
17.12.14
出生時のビタミンD濃度と自閉症スペクトラム発症リスクとの関係
出生時のビタミンD濃度は3歳時の自閉症スペクトラム発症リスクに関連することが中国で実施された症例対照研究で明らかになりました。
17.12.13
生活習慣・食事・サプリメント男性の妊娠させる力に影響を及ぼすもの
男性不妊患者へのビタミンDの補充効果:無作為化比較対照試験
ビタミンDが不足している男性不妊患者のビタミンDとカルシウムのサプリメント補充は精液所見の改善やパートナーの出産率への効果は見出せませんでしたが、乏精子症の男性に限ればパートナーの出産率が向上することがデンマークで実施された無作為化比較対照試験によって明らかになりました。