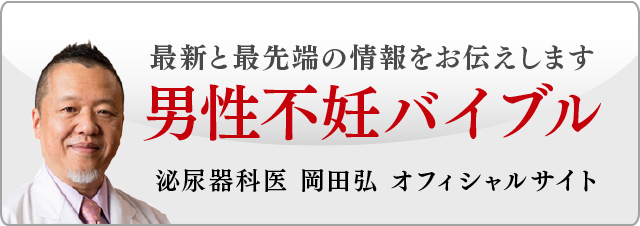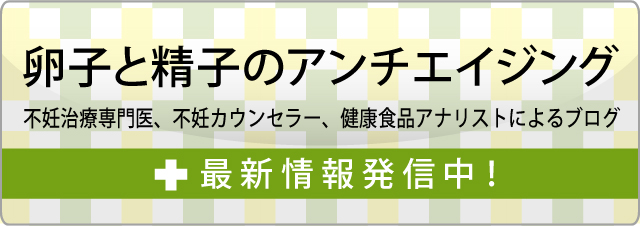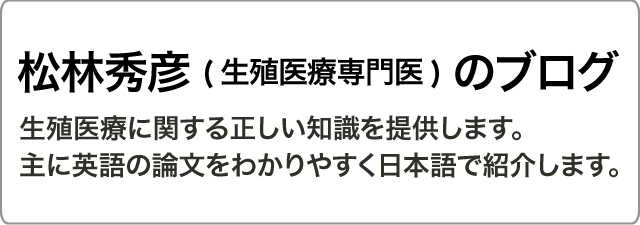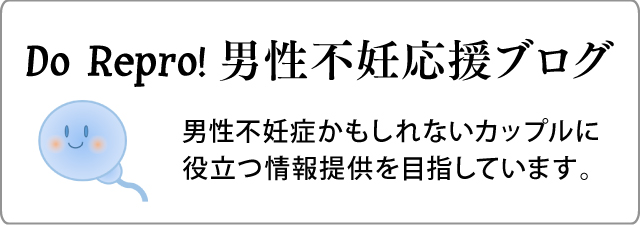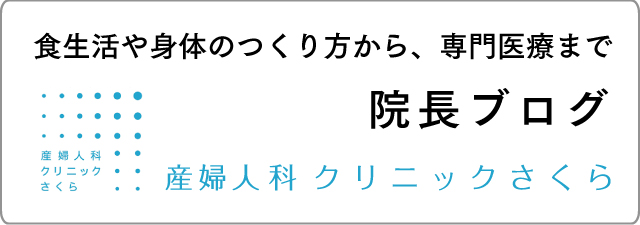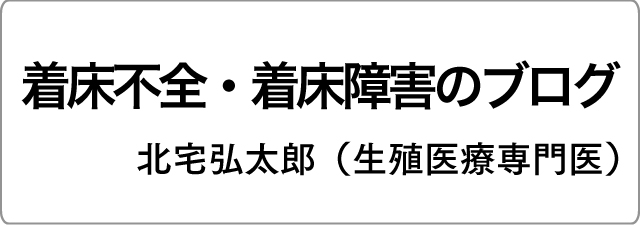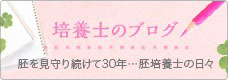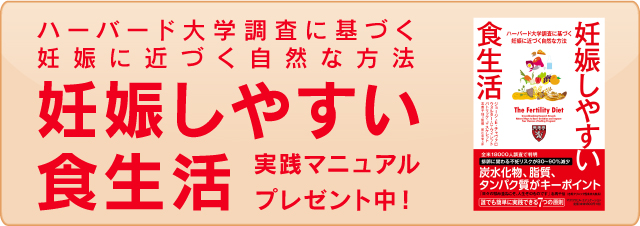____________________________________________________________________
妊娠しやすいカラダづくり No.1152 2025/7/27
____________________________________________________________________
今週の内容__________________________________________________________
・最新ニュース解説:妊娠前のカップルのアルコール摂取と流産の関係
・編集後記
最新ニュース解説 Jul, 2025__________________________________________
妊娠前のカップルのアルコール摂取と流産の関係
-----------------------------------------------------------------------
妊娠前のアルコール摂取は、カップルのいずれのアルコール摂取量やアルコールの種類においても、流産リスクの増加と関連しないことが、北米で実施された研究で明らかになりました(1)。
北米の1万人以上の妊娠希望のカップルを対象とした前向きコホート研究、PRESTO研究のデータを用いた研究でわかったことです。
カップルのアルコール摂取と流産の関係については、これまでもいくつもの研究が実施されていますが、相反する結果が報告されていたり、研究方法にばらつきがあり、エビデンスが定まっていませんでした。
そこで、スタンフォード大学の研究者らは、大規模のウェブベースの前向きコホート研究であるPRESTO研究のデータを用いて検討されました。
◎どんな研究だったのか?
2013年6月から2023年5月迄に、この研究に参加登録したカップルにオンラインアンケートで、前月の週ごとのアルコールの平均摂取量を、アルコールの種類別に回答してもらいました。
アンケートは、参加時、その後は8週間毎に回答してもらい、妊娠に至る迄、もしくは、最大1年間続けられました。
アルコールの種類で摂取量を標準化するため、週平均のアルコール摂取量は、アルコールの種類から摂取したアルコールのグラム数を合計し、12で割ることで標準サービング(1サービングあたり12gのアルコール)に換算されました。
女性参加者には妊娠や流産に関して報告してもらい、カップルの妊娠前のアルコール摂取と流産率との関連が解析されました。
◎どんな結果だったのか?
女性9,414名(平均年齢30歳)と男性2,613名(平均年齢32歳)からデータが得られました。
女性の27%、男性の20%が妊娠前にアルコールを飲んでいませんでした。
妊娠の約20%が流産で終了しました。
流産リスクに影響を及ぼす因子を調整した結果、妊娠前のアルコール摂取と流産との間に有意な関連性は見出されませんでした。
この結果は、アルコールの種類(ワイン、蒸留酒、ビール)、年齢、流産歴、妊娠週数によって、解析されても、変わりませんでした。
◎アルコール摂取の不妊治療成績に及ぼす影響は?
アルコール摂取の妊娠への影響についても、多くの研究が実施されています。
たとえば、デンマークのオーフス大学病院で不妊治療受けた1708組のカップルを対象にした研究があります(2)。
治療開始前に週あたり平均的な飲酒量を研究開始時と以後の治療開始時に質問票にて回答してもらい、その後の人工授精1511周期、体外受精/顕微授精2870周期、そして、凍結融解胚移植1355周期の妊娠率や出産率との関係が調べられています。
飲酒量はアルコール12g(デンマーク基準)を1単位として、週あたりのビールやワイン、蒸留酒の飲酒量を、飲まない、1-2単位、3-7単位、7単位以上の4段階にわけ、1-2単位を少量、3-7単位を中程度、7単位以上を多量としています。
解析の結果、週あたり少量から中量の飲酒は人工授精やARTの妊娠率や出産率と関連しなったとのことです。
◎アルコール摂取時期によって妊娠への影響が異なる可能性がある
アルコール摂取と妊娠しやすさの関係については、女性の生理周期中のどの時期に飲むかで影響が異なるという研究報告があります(3)。
週に6杯以上の飲酒は、卵胞(低温)期でも、黄体(高温)期でも、妊娠率低下に関連しますが、黄体期では、週に3-6杯の飲酒量でも妊娠率低下に関連するというもので、飲酒量だけでなく、飲酒のタイミングも妊娠しやすさに影響するとの報告です。
研究は、アメリカの14州の19-41歳のオフィスワーカーの女性413名に、毎日、どんな(ビール、ワイン、蒸留酒)アルコールを、どれくらいの量を飲んだのか、毎日記録し、かつ、妊娠判定のために毎月尿検体を提供してもらい、最長19ヶ月追跡し、月経周期中の卵胞期、排卵期、黄体期の3フェーズのアルコール摂取路量と妊娠率の関係を調べています。
その結果、卵胞期や排卵期では週に6杯以上の飲酒は、妊娠率が、それぞれ、飲まない女性に比べて46%、61%低下しました。ただし、卵胞期の妊娠率の低下は、妊娠希望の有無や月経周期で解析し直してみると妊娠率の低下はみられなくなったとのことです。
その一方で、黄体期には週に6杯以上の飲酒で、飲まない女性に比べて妊娠率が49%低下しただけでなく、週に3-6杯程度でも、妊娠率が41%低下したというのです。
また、1日に4杯以上過飲する日が1日増えるごとに、妊娠率は飲まない女性に比べて排卵期では41%、黄体期では19%、それぞれ、妊娠率が低下しました。
◎妊娠計画後は控えるのが無難
妊娠中のアルコール摂取は、胎児の発育に悪影響を及ぼすため、禁酒が推奨されることはもちろんのことです。
ただし、妊娠初期の影響についても明らかになっていますので、日本産婦人科学会では、妊娠を希望する時期から禁酒を推奨しています。
妊娠が判明する前の時期の飲酒も、胎児に影響を与える可能性があると考えられているからです。
文献)
1)Reprod Biomed Online . 2025; 51: 104698
2)Hum Reprod 2019; 34: 1334.
3)Hum Reprod 2021; 36: 2538
--------------------------------------------------------------------
記事についての感想やご意見は下記のアドレス宛お寄せ下さい。
info@partner-s.info
編集後記____________________________________________________________
飲み過ぎに注意しつつ、妊娠の可能性がある時期からは控えるのが無難です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
妊娠しやすいカラダづくり[毎週末発行] VOL.1152
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お子さんを望まれるカップルの"選択"や"意志決定"をサポートします。
--------------------------------------------------------------------
不妊に悩むカップルが、悩みを克服するために、二人で話し合い、考えを整理して、自分たちに最適な答えを出すためのヒントになるような情報を、出来る限り客観的な視点でお届けしています。
--------------------------------------------------------------------
発 行:株式会社パートナーズ
編 集:細川忠宏(日本不妊カウンセリング学会認定不妊カウンセラー)
企業サイト:https://partner-s.info/
情報サイト:https://www.akanbou.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎発行部数
・自社配信: 1,692部
・まぐまぐ: 1,986部
・合計部数: 3,678部(7月27日現在)
--------------------------------------------------------------------
◎免責事項について
当メールマガジンの提供する情報は医師の治療の代わりになるものでは決してありません。プログラムの実行は各人の責任の元で行って下さい。プログラムの実行に伴う結果に関しては、当社の責任の範囲外とさせて頂きます。
--------------------------------------------------------------------
◎注意事項
読者の皆さんから寄せられたメールは、事前の告知なく掲載させていただく場合がございます。匿名などのご希望があれば、明記してください。また、掲載を望まれない場合も、その旨、明記願います。メールに記載された内容の掲載によって生じる、いかる事態、また何人に対しても一切責任を負いませんのでご了承ください。
--------------------------------------------------------------------
◎著作権について
当メールマガジンの内容に関する著作権は株式会社パートナーズに帰属します。一切の無断転載はご遠慮下さい。