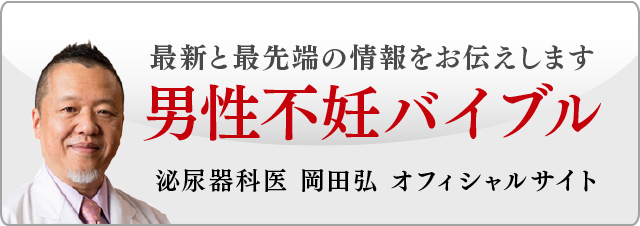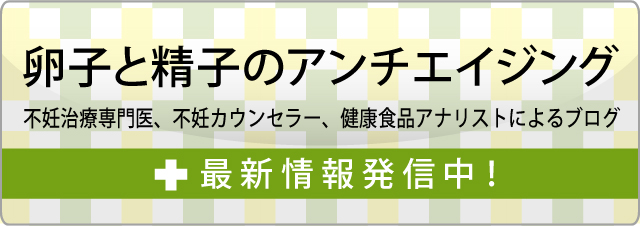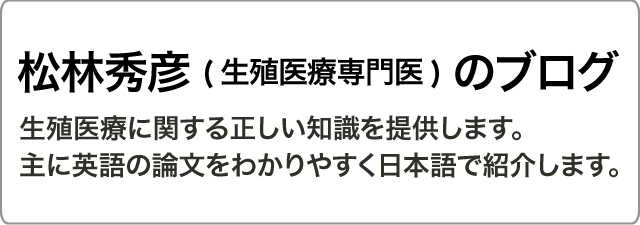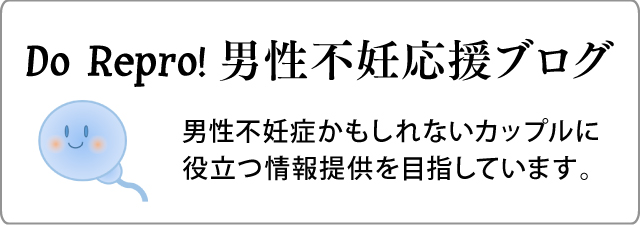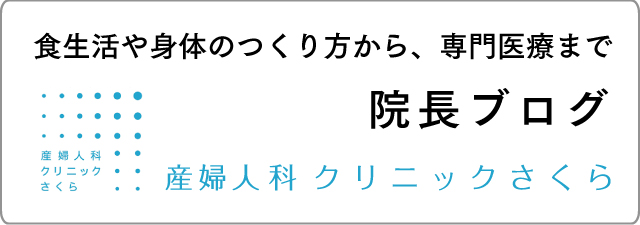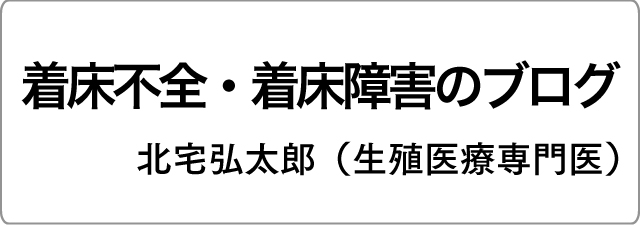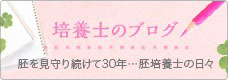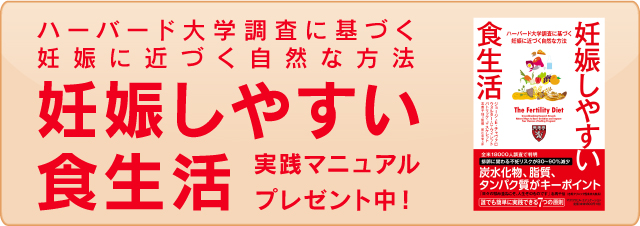魚に豊富に含まれるオメガ3脂肪酸であるEPAやDHAの摂取量が多い女性はフタル酸エステル類による生殖機能への有害な影響が軽減されるという、最新の研究報告がアメリカのハーバード大学によってなされています。
フタル酸エステルはプラスティック製品を軟らかくする化学化合物として、化粧品原料や食品用の容器、包装、さらには、洗剤、医療用品にまで、生活環境に広く存在しています。
一方で、精液の質の低下や採卵数の低下、ART治療後の生児獲得率の低下、早産や流産リスクの上昇など、生殖機能への有害な影響が報告されています。
そのため、近年では世界的に規制が進んでいますが、まだまだ、自然界では大気や水、土壌など様々な環境中から検出され、環境汚染物質として懸念されています。
そのフタル酸エステルの生殖機能への有害な影響がDHAやEPAによって打ち消される可能性があるというのです。
必須栄養素をはじめとした栄養素の中には、エネルギーを産生したり、身体をつくったり、身体の機能を調節したりするという働きだけでなく、化学物質の害を軽減してくれる働きも備わっているものもあるようです。
たとえば、魚に高濃度に含まれるメチル水銀は神経毒性、特に胎児の発達に影響を及ぼす可能性が懸念されていますが、必須ミネラルのセレンは水銀と結合し、無毒で安定な化合物(セレン化水銀)を形成するため水銀の毒性を軽減する働きがあることが知られています。
また、DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)は、かつて広く使用された有機塩素系殺虫剤で、急性毒性は低いものの、環境中での残留性が高く、生物濃縮されるため、生態系に悪影響を及ぼすことが指摘されています。
ところが、ビタミンB12が充足している女性ではDDTレベルと妊娠率は関連しませんが、ビタミンB12が不足し、かつ、DDTレベルが高い女性では妊娠率が低く、ビタミンB群濃度とDDT、妊娠率との相互作用が確認されており、ビタミンB群にはDDTの生殖機能への有害性に対する抑制作用があることはわかっています。
さらに、ビスフェノールA(BPA)は食器や容器などに使用され、そこから溶けだし、体内に取り込まれ、健康への影響が懸念、特に乳幼児への影響が問題視されています。
ところが、大豆食品の摂取量や葉酸濃度が低い女性ではBPA濃度が高くなるほど妊娠率が低くなる一方、大豆食品の摂取量や葉酸濃度が高い女性ではBPA濃度が高くなっても妊娠率は低下しないとの研究報告がなされており、大豆食品や葉酸にはBPAの生殖機能へのマイナスの影響を打ち消す作用があります。
葉酸には大気汚染物質による生殖機能の低下を緩和するという報告までなされています。
現代社会では、化学物質は日常生活における利便性を飛躍的に高めた反面、環境汚染や健康、特に生殖機能に有害な影響を及ぼすリスクが伴うようになってしまいました。
適切な管理が大切ですが、人体に取り込まれることを徹底的に避けようとしても限界があります。
そのため、新鮮な野菜や魚、大豆食品を中心に、バランスよく食べることで、体内の有害物質のマイナスの影響を軽減する働きを高めるほうが現実的です。
反対に、加工食品を多量に食べることは、有害な化学物質を取り入れやすくなるだけでなく、栄養バランスの悪化で必須栄養素が不足するリスクが高くなり、有害物質の害に対する抵抗力も弱くなってしまいます。